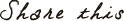日本の工芸を元気にする。中川政七商店が掲げるビジョン
「中川政七商店」が誕生したのは300年も前のこと。
1716年、初代の中屋喜兵衛が奈良晒の問屋業を起こしたのが、中川政七商店の始まりです。
ピーク時の1/5以下にまで減少した「日本の工芸」。
日本全国、人の手によって生み出されるこの「工芸」を残して行きたいという想いを掲げ、工芸の魅力を再発見させてくれるようなラインナップが充実していることが中川政七商店の特徴です。
100年後も日本の工芸が生活の中に溢れているように。みなさんもぜひ一度「中川政七商店」のアイテムを手に取ってみてください。
生活を心地よくする、中川政七商店のアイテム9選
【1】「麻の葉もなか」や「月ヶ瀬茶」のブリキ缶
中川政七商店と言えばこのアイテム。
このブリキ缶は見たことがあるという方も多いのではないでしょうか?
本来は「麻の葉もなか」や「月ヶ瀬茶」のパッケージとして販売されているものですが、この空き缶をお弁当箱として使うのがとても人気なのです。
絶妙なサイズ感と詰めやすい長方形の形が重宝される理由です。
【2】吹き寄せ
中川政七商店の店舗に入って一番に目につくのがこちらの「吹き寄せ」ではないでしょうか?
季節ごとに展開される素敵なお菓子の詰め合わせ。
蓋を開ける愉しみも、ぎっしりと詰まった色とりどりの可愛らしいお菓子も、どこか懐かしいワクワク感を思い出させてくれます。
いつものティータイムが少し豪華になる宝箱のような吹き寄せ。そのままお茶菓子にするのもよし、自家製のおやつにプラスするだけで、豪華なスイーツがおうちで楽しめます。
お菓子を全て食べきったあとは、こんな風に使うのもいいですね。
柔らかな色合いが素敵な缶も大切に使いたい一品です。
【3】ごはん粒のつきにくい弁当箱
内側の塗装に粒子が細かい特殊素材を使うことにより、ごはん粒がつきにくく、汚れが落としやすい仕様になっているお弁当箱。
「山中漆器」の産地、石川県加賀市にあるお弁当箱メーカー「たつみや」さんの技術によって作られたお弁当箱です。
塗りの技術が極めて高いおかげで一見漆製品に見えますが、こちらは樹脂製。仕切りもなく、液漏れの心配もなし、食洗機にもかけられるという優れもの。
私、次のお弁当箱はこれに決めました!
【4】塩をさらさらに保つ塩壺
常滑市の窯元「山源陶苑」とともに作られた「塩をさらさらに保つ塩壷」。
中の湿度を一定に保ち、湿度の変化で固まってしまう塩をさらさらのまま保存することができます。
キッチンに置いておくだけで素敵な佇まい。
入れ物にこだわると、塩自体もこだわりたくなってきます。
【5】かや織ふきん
中川政七商店に行くと記念品のように必ず買ってしまうもの「かや織 掛けふきん」。季節やイベントごとに入れ替わるデザインはいつ見ても新鮮で楽しい。
丈夫で使いやすく、使い込むほどに愛着のわくふきんです。手土産やちょっとした贈り物にも必ず入れています。
【6】鹿の子編みのキッチンスポンジ
奈良の編地の専門メーカー、「タツミセンイ株式会社」とともに作られたキッチンスポンジ。
昭和生まれの貴重な機械で熟練の職人が微調整しながら編んだ鹿の子編みのネットは、きめ細やかな泡立ちと汚れ落ちの良さ、乾きやすさが特徴です。
【7】綿麻ふんわりアームカバー
靴下の生産地として知られる奈良県の靴下屋さんとともに作られたアームカバー。
夏の紫外線対策としてはもちろん、肌寒い時にも役立つアームカバーはカバンに入れておきたい便利アイテム。
中川政七商店らしいデザインとカラーバリエーションの豊富さは、アームカバーの作業着感を払拭できます。屋外スポーツや庭仕事にもぴったりです。
【8】「かもしか道具店」ごはんの鍋
一枚蓋だけど吹きこぼれの心配もなく、ふっくらおいしい土鍋ごはんが炊けるかもしか食堂「ごはんの鍋」。こちらの土鍋、1合炊きの小さなお鍋から販売しているので、一人暮らしのおうちにもぴったりですよ。
なんと、「ご飯を美味しく炊く」を追求するため、かもしか道具店の社員総出で様々なサイズの鍋を使って炊飯したそうです。その結果をふまえて、1合・2合・3合のお米に合った鍋サイズを設計したんだとか。
毎日ごはんを炊くのが楽しくなるお鍋です。
【9】「庖丁工房タダフサ」パンくずが出ないパン切り包丁
パン切り包丁って刃先が波打っているものがほとんどですが、こちらのパン切り包丁は切り口がなめらかで、パンくずがほとんどでないのが特徴。
刃の先端部分のみ波刃になっているので、硬いフランスパンにもすっと切り込みが入ります。
タダフサの特許技術から生まれた抗菌炭化木にした栗材をハンドルに使用するなど老舗の技術が光る一品。高価だけど一生モノとして長く使い続けることのできる「最後のパン切り包丁」はいかがでしょうか?