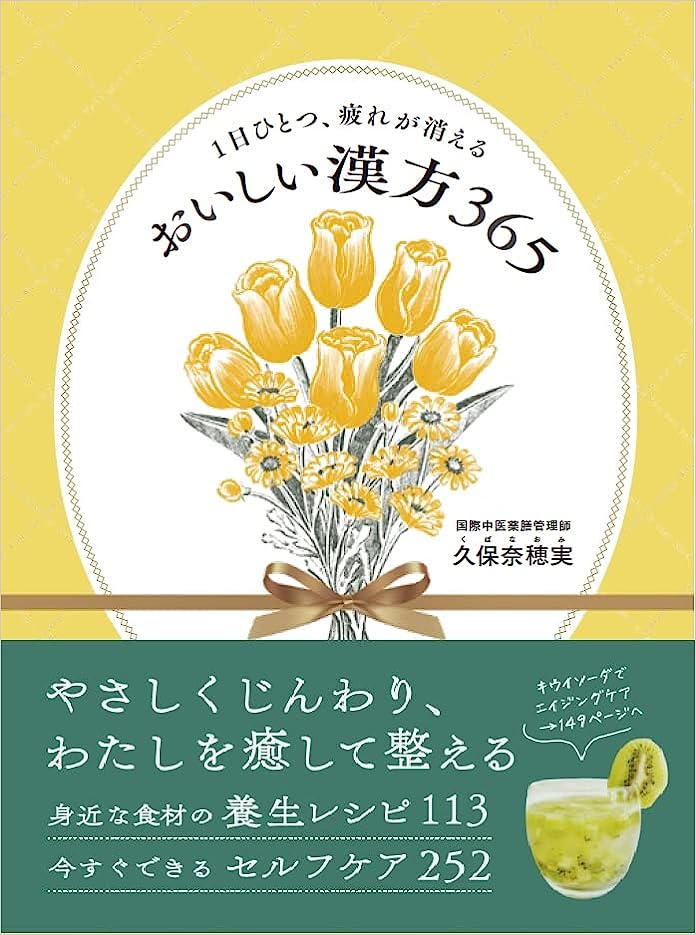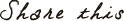一年で最も暑さが厳しい大暑
「大暑(たいしょ)」は、暦の上で一年で最も暑さが厳しくなる時期。二十四節気の12番目で、夏を6つに分けたうちの最後の節気です。

例年、7月23日頃が大暑の時期にあたります。
「夏の土用」の時期でもあり、全国各地のお祭りや花火大会もこの時期にたくさん行われる夏真っ盛りの時期ですね。
8月は暦の上ではすでに秋に入っていますが、実際は毎日猛暑日続き。夏バテして体調を崩してしまっている方も多いようです。
夏のクールダウンにおすすめの養生レシピ
暑さが厳しいとどうしても夏バテしてしまいがち。とはいえ、暑いからといってアイスや冷たいドリンクばかりを摂っていると、胃腸を冷やし、さらに夏バテを招いてしまいます。暑さをクールダウンしたい場合には、涼性や寒性食材を上手に取り入れるのが◎。
今回は、夏のクールダウンにおすすめの養生レシピをご紹介します。
どのレシピも、分量は適量でもおいしく作れるレシピになっています。
苦みで熱冷まし!「ゴーヤのさっぱり塩昆布和え」

体の熱を冷ましてくれる「ゴーヤ」を使った一品。
ゴーヤは火を通しすぎず、高い温度で調理せずに苦みも残すほうが清熱作用を保つことができます。クールダウンには、天ぷらや油炒めよりも、さっとゆでて作るレシピがおすすめ。
ゴーヤのシャキシャキ感と苦みを存分に楽しめる夏らしいレシピです!
作り方
1. ゴーヤを縦半分に切って、種とワタを取り薄切りにし、サッと塩ゆでして(湯にくぐらせる程度)水で冷ます。
2. 1の水気を絞り、せん切りにしたみょうがと塩昆布で和える。
夏の食欲不振には「ちくわときゅうりのサッパリ和え」

夏の食欲不振からくるだるさに。
ちくわの原料の白身魚は胃腸に優しいうえ、元気を補う力が強いので、疲れを取ってバリア機能を高めてくれます。
きゅうりは熱を冷まし、余計な湿を取り除いてくれるので、重だるさもスッキリ! 黒酢は、血を巡らせてコリによるだるさを改善してくれます。
作り方
1. ちくわときゅうりを輪切りにする。
2. 1を黒酢(なければ米酢)、醤油、ごま油、黒糖(少々)で和える。
夏バテに「モロヘイヤスープ」

寒暖差疲れや夏バテには、栄養価が高く「野菜の王様」と呼ばれるモロヘイヤがおすすめ。
モロヘイヤは、体の熱を取り、内側から潤してくれる、夏バテにぴったりの食材。イチオシのレシピは「モロヘイヤスープ」です。
トロトロして飲みやすいので、食欲がないときにぜひ!
作り方
1. みじん切りのにんにくを油で炒めて水を加え、沸騰したら刻んだモロヘイヤを加えて弱火で軽く煮る。
2. 塩と鶏がらスープの素を加えて味を調え、ごま油を回し入れる。煮込みすぎず、シャキシャキしてるくらいがおいしいです。
体にこもった熱をしっかりと排出しよう
暑い〜暑い〜って、ついつい冷たい飲み物やアイスばかり食べていませんか?
アイスを食べると涼しくなってクールダウンしたように感じますが、実はアイスには体の熱を冷ます働きはないんです。お腹は冷えるのに、体にこもった熱はそのまま。おまけに砂糖も乳脂肪もたっぷりなので、湿をため込み、体は重だるになる一方なので、食べすぎにはご注意を。
暑いときはアイスより寒天
アイスの代わりにおすすめなのが寒天。寒天は海藻からできていて、体にこもった熱をスーッと冷ましてくれます。(ちなみに、ゼリーは湿をため込みます)
暑いときには、ぜひ熱を排出してくれる寒天を摂るようにしてみてください。
クーラーを上手に味方にする

クーラーはなんとなく体に悪いイメージをもたれがちですよね。
もちろんガンガンに冷やすと不調の原因になりますが、適度に使えばむしろ体の負担を減らしてくれるので、快適に過ごすことができます。
ここ数年は昔と違って、熱帯夜で危険な暑さを感じる日もありますよね。夜中にタイマーでオフにすると、汗をたくさんかいて目が覚めてしまうので、直接風が当たらないようにして「うっすらかけっぱなし」で寝るのがおすすめです。
クーラーを上手に味方につけて、養生レシピも取り入れながら、夏の暑さを乗り切りましょう。
記事監修・レシピ考案:国際中医薬膳管理師 久保奈穂実
国際中医薬膳管理師。漢方アドバイザー。成城漢方たまりで年間約2000人の漢方相談・薬膳講師を行う。女子美術大学造形科卒業。芸能・音楽活動を行い、ハードな生活で身体のバランスを崩す。漢方薬に助けられた経験から興味を持ち、イスクラ中医薬研修塾にて中医学を学ぶ。SNS にて発信するやさしい養生知識や、カンタン薬膳レシピが大人気。総フォロワー約9万人。