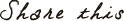今日はどの鍋で温まろう?
【北海道】石狩鍋
北海道を代表する郷土料理の1つ「石狩鍋」は、鮭で有名な石狩川の河口にある石狩町が発祥とされています。
石狩地方では江戸時代から鮭漁が盛んで、大漁を祝う際、漁師たちがとれたての鮭を豪快に鍋にして味わったことが起源とされているのだとか。
作り方は、ぶつ切りした鮭の身とあらを野菜と一緒に昆布の出汁の中に入れて、味噌で味を調えたら出来上がり。具材はたまねぎやキャベツ、長ねぎ、大根、しいたけ、豆腐などで、最後にいくらを乗せて贅沢に味わったり、バターでコクをプラスしたりしても。
旅先のご当地グルメをキャンプで作るのが好きだという@y___namiさんは、北海道にある日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖そばのキャンプ場で石狩鍋作り。市販の鍋つゆを使ってとても簡単にできたそう。
◆材料
•味噌鍋つゆ
•鮭の切り身
•帆立
•椎茸
•豆腐
•白ネギ
•春菊
◆作り方
鍋つゆを鍋に入れて沸騰させます。
沸騰したら材料を入れて煮込んで完成です!
味噌を使ったお鍋は体がポカポカと温まるので、寒い日にぴったり。こんなふうにキャンプでワイワイと楽しめば、忘れられない思い出の味になること請け合いです。
【秋田】きりたんぽ鍋
米どころ、秋田の郷土料理「きりたんぽ」は、炊き上げたお米を木の棒に塗りつけて、炭火で焼いたもの。冬期に狩猟を行う猟師が保存食として携行したのが起源とされていて、今では冬季の給食メニューとしても人気です。
これを切って鍋に入れたのが「きりたんぽ鍋」で、地鶏やごぼう、きのこ、ねぎなどと一緒に鶏ガラの出汁で煮込んで作ります。
@uchikocさんの「きりたんぽ鍋」は、きりたんぽのほか、鶏もも肉、手羽中、ごぼう、舞茸、ねぎ、三つ葉を入れて。具だくさんでとってもおいしそうですよね。
お汁は大量の鰹節でとった出汁の中に鶏もも、手羽中を入れて低温で2時間近く焚いたもの。手羽中入れると鶏の出汁が濃厚になるそうなので、ぜひお試しを!
【山形】芋煮鍋
里芋やこんにゃく、ねぎ、きのこ類、季節の野菜などを主な具材とした山形の郷土料理「芋煮」。
ルーツは1600年代半ば、当時の最上川舟運の船頭たちが、仕事の合間の退屈しのぎに作ったのが始まりだと伝えられています。今では、河原で芋煮の鍋を囲む芋煮会は、山形の秋の風物詩です。
具材と味付けは地域によって微妙に違い、庄内地域は豚肉に味噌味、最上地域と村山地域は牛肉に醤油味、置賜地域は牛肉に醤油味で隠し味に味噌を入れるそう。
@49campsさんがキャンプで味わった「芋煮鍋」は、山形県出身者が作る本格派。味の決め手は山形産の醤油で、お鍋から溢れ出しそうな豪快な見た目にもそそられます。
そして、〆はカレールウを入れてカレーうどんに。旨味たっぷりのカレースープも最高で、最後の最後まで幸せな時間が続きます!
【茨城】あんこう鍋
「あんこう鍋」は、茨城県北部の町、平潟で漁師たちが食べていた「どぶ汁」がルーツ。「とぶ汁」とは、水を全く使わずに、具材のあんこうと野菜から出る水分にあん肝を溶かして煮込んだ料理です。
「あんこう鍋」の味付けは醤油か味噌が定番で、あんこう以外の具材は白菜やにんじん、ねぎ、えのき、豆腐、しらたきなどお好きなものでいいんです。
@naocafeさんは、あん肝がなかったため、ホタルイカを入れて旨味をプラス。熱燗にぴったりの味わいだったそうですよ。
あんこうの旬は11~2月で、冬の味覚を代表する魚。身だけでなく、皮や内臓など骨以外のすべてを食べられるので、お鍋にして丸ごと味わいたいですね。
【東京】ねぎま鍋
「ねぎま鍋」と聞くと、焼き鳥の「ねぎま」を入れた鍋かな?と思ってしまいそうですが、漢字で書くと「葱鮪鍋」。ねぎとマグロを醤油、日本酒、みりん、出汁などで煮た鍋料理のことです。
そのルーツは江戸時代にまでさかのぼります。当時、マグロは赤身が重宝されていて、脂のあるトロは余りものでした。そこで江戸の庶民は、お安く手に入るトロとねぎを煮て、「葱鮪鍋」にしたそう。
@t.shimizu019さんは、そんな江戸の味を再現したくて、大トロを投入! なんとも贅沢で、こんがりと良い色に焼けたねぎも食欲をそそります。
【山梨】ほうとう鍋
「ほうとう」は、小麦粉を練った平打ち麺を、かぼちゃなどの野菜とともに味噌仕立ての汁で煮込んだ、山梨を代表する郷土料理。古くは戦国武将、武田信玄が陣中食にしていたとも伝えられています。
麺のモチモチとした食感と、とろみのついた旨味たっぷりの汁は、一度食べたらやみつきになるほどのおいしさです。
こちらのお写真は、フリーアナウンサーの大橋未歩さん(@o_solemiho815)お手製のほうとう鍋。お肉や野菜がたっぷり入って栄養満点ですね!
大橋さんは神戸出身ですが、ほうとう鍋が大好きで、秋田の「きりたんぽ」も大分の「やせうま」も大好物なのだそう。
ちなみに、「やせうま」とは、小麦粉で作ったひらたい麺状の生地にきなこと砂糖をまぶして食べる、大分の定番おやつ。おうちにある材料で簡単に作れるので、こちらもぜひ試してみては。
【大阪】てっちり
高級魚のふぐを主役にした鍋料理「てっちり」。こう呼ぶのは大阪の方が多く、ふぐの本場、山口県などでは「ふぐちり」の名前で愛されています。
出汁には、ふぐの淡泊な味を引き立てる昆布を使うのが一般的。肉厚でぷりぷりのふぐを野菜やきのこ類と一緒に煮て、ポン酢をつけて食べると絶品です。
@cao_lifeさんは、お酢と醤油で自分好みのポン酢が作れる「今塩屋佐兵衛 とうがらしポン酢の素」をつけて。ほどよい辛さが食欲を刺激して、食もビールもどんどん進んでしまいそうです!
【広島】牡蠣の土手鍋
味噌を鍋の内側に土手のように塗り付け、カキや豆腐、野菜を煮ながら食べる「牡蠣の土手鍋」。西の三大鍋ともいわれていて、広島県では昔からなじみのある人気の鍋料理です。
発祥については、行商人が考案したという説などがあるそう。
@mayu0033さんの「牡蠣の土手鍋」は、彩り豊かでとてもきれいですね。〆は細うどんを入れて楽しんだそう。
真牡蠣は冬が旬。うま味が濃縮されたクリーミーな味わいを、ぜひお鍋で楽しんでみては。
【福岡】水炊き
博多を代表する郷土料理「水炊き」の生みの親は、長崎出身の料理人・林田平三郎さん。明治30年、林田さんが15歳で単身香港に渡って洋食と中華料理にヒントを得て考案し、博多で水炊きの店「水月」を開業したのが始まりなのだとか。
今や全国で食べられている水炊き。博多では、鶏肉や野菜の旨味を生かし、水から煮立たせて作ります。
そんなに寒くない日は、@bijou7231さんのようにあらかじめ煮立たせた鍋を鍋敷きの上に置いて味わっても。こんなふうにかわいい鍋敷きだと、よりテンションが上がりますね。
目指せ、ご当地鍋で日本一周!
地元のご当地鍋は入っていましたか?
ほかにも、猪の肉を使った静岡県の「ぼたん鍋」や天然の真鴨を食材とした滋賀県の「鴨鍋」、鶏肉や魚を椿油で炒ってから鍋にする長崎県対馬の「いりやき鍋」など、気になるご当地鍋がたくさんあります。
現地に食べに行ったり、おうちで作ったりして、ご当地鍋で日本一周してみるのも楽しそうですね。