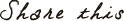一番身近なうつわ、洋食器
洋食器の数の方が多いというご家庭も少なくないのではないでしょうか?
手で持ちお箸を使って食べる和食気器とは違い、テーブルに置いて、ナイフとフォークを使う洋食器は、その食べ方に合わせ、重く傷の付きにくい素材でできています。
食文化の違いでうつわも変化していると考えると、お皿選びがより楽しくなってきませんか?
以前は和食器編をご紹介しましたが、今回は洋食器のサイズについてご紹介したいと思います。
和食器編と比較してみると楽しいかもしれませんね♪
洋食器のサイズ
和食器は○寸というサイズで表しますが、洋食器は使い方や名前によってサイズが分けられています。
和洋問わず、「何を盛り付けるのに向いているサイズなのか」という目安になるので覚えておくといいかもしれません。
プラター(約27cm~33cm)
30cm前後のワンプレートやメインの料理にぴったりの大皿を「プラター」と呼びます。
オードブルなんかにも良いですね。2人家族でも1枚あるとなにかと便利です。
ラウンド型だと結構場所をとるので、ダイニングテーブルが小さめという方は写真のようなオーバル型やスクエア型がオススメです。
メインディッシュ(約23cm~27cm)
「メインディッシュ」はパスタやカレーを盛り付けるのに最適なサイズ。
ちょっとしたワンプレートにも使えます。
大き目のメインディッシュであればトーストをのせてもまだまだ余裕があるサイズです。
オーバルプラターだと収納場所に困るという方にもオススメです。
デザートディッシュ(約21cm)
もっとも使い勝手が良いと言われる「デザートディッシュ」。
ちょうど食パン1枚がのる大きさです。
デザートディッシュだからと言ってデザートしか使えないわけではありませんよ!
1人分のおかずを盛り付けるのにちょうど良いサイズです。
女性だったらメインディッシュとしても使えそうですね。
ライス皿(約19cm)、パン皿(約17cm)
「ライス皿」「パン皿」は洋食屋さんでライスやパンを頼んだ時に出てくるお皿というとイメージがわきやすいでしょうか。
どちらも取り皿として使いやすいサイズです。
何枚あっても使えるので様々なデザインバリエーションを集めたいですね。
インスタで人気の洋食器をご紹介!
大皿といえばこれ!Rorstrandのモナミでテーブルを華やかに
スウェーデン王室御用達の釜として創業したRorstrand(ロールストランド)。
プレートにもパーティーにももってこいの大皿がインスタでは人気です。
テーブルコーディネートが苦手な方でもこのお皿一枚で上級者風♪
シンプルで使いやすいiittalaのティーマはサイズ違いでそろえたい
汎用性の高さでは右に出るものはいないほど、使いやすく大人気のティーマ(Teema)。
15cmから26cmの豊富なサイズ展開と使いやすい5色のカラーが人気インスタグラマーを魅了しています。
@mayumimiyaharaさんのようにプラターサイズにスキレットを置く見せ方はぜひ真似したいアイデア!
一枚は持っておきたいARABIAのパラティッシ
ARABIA(アラビア)のお皿はどれも非常に人気ですが、代名詞とも言えるパラティッシはラインでそろえたいほど素敵…!
サイズも4種類あるので、用途に合わせてぴったりのサイズを探してみてくださいね。
一見すると派手なデザインですが、これが意外とどんな料理にも合う不思議!
ブラック、イエロー、パープルと3色ありますが、あなたはどれを選びますか?
陶器の質感がほっこりするmina perhonenのタンバリンプレート
テキスタイルメーカーとして有名なmina perhonen(ミナ ペルホネン)のタンバリンプレートは洋食器では珍しい温かみのある陶器で作られたお皿です。
17cmのパン皿と23cmのメインディッシュがあります。どちらも使いやすいサイズですね。
わが家でも愛用していますが、朝食にタンバリンプレートを使うと一日のテンションがぐっと上がります(笑)。
一つ一つ専用のかわいい箱に梱包されているのも嬉しいポイント。
デリスタグラマーはみんな持ってる?!イイホシユミコさんのアンジュール
陶器作家イイホシユミコさんのアンジュール(unjour)は、インスタグラムで見ない日はないくらい大人気のお皿。
カラーバリエーションも優しい色合いが多く、シンプルな形なのでどんな料理にも合わせやすそうです。
梱包されている箱もおしゃれなので気になる方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか?
うつわを知ることは食文化に触れること
二回にわたってご紹介してきました、「お皿のサイズシリーズ」はいかがでしたでしょうか?
洋食器も和食器も、知れば知るほど欲しくなるし、どんなお皿にどんな料理や食べ方が合うのかを考えていると、挑戦したい料理も増えてくるのではないでしょうか?
お皿を知ることでその国の食文化に触れることができるのはとっても興味深いですよね。
この記事でご紹介したことが少しでもみなさまの食卓を彩るきっかけになれば嬉しいです!